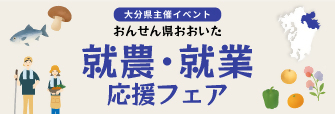"三方よし”の精神で挑む!
白ネギの高冷地栽培のパイオニア
由布岳を眺める閑静な別荘地を抜けた先、荒涼とした冬枯れの草原の中に佇む銀色の倉庫。ここで白ネギ農家を営むのは、神奈川県出身の坂田章太さんです。
大分県に住む祖父の影響で、中学生の頃から農家を志していた坂田さんは、高校卒業後、大分県の農業大学校へ進学し、研修先として訪れた豊後高田市の「仲井農園」に就職。9年間、白ネギの栽培担当を任された後、2021年に「ネギの坂田」として独立しました。
「台風が来ればネギに何かあったらどうしようとへこみますし、ネギの出来が良ければ本当に宙を舞うほどうれしくなるんです」。
そう一喜一憂する姿は、まるで白ネギに恋する青年のようです。


周囲を見渡すと剥き出しの自然が広がる
独立するにあたって、由布市で何十年と耕作放棄地だった牧場跡地を借り受けた坂田さん。最初に取り掛かったのは、雑木林と化した土地を切り開くところからでした。
「当時は、この倉庫が外からは見えないくらい鬱蒼としていた」とか。
さぞ大変なところからのスタートだったのだろうと思いきや
「もともと農業に興味を持ったきっかけは、玖珠町で林業や原木椎茸の栽培をしていた祖父の影響でした。祖父の軽トラに乗って山へ行って手伝いをするだけで、周りに何もなくても十分楽しかった。当時の記憶が原体験となっていたので、土木系の作業も嫌いじゃないんです(笑)」と坂田さんは声を弾ませます。
年間売上2000万円。主な卸先は、JAや大手スーパー、カット野菜工場、給食センターなど。露地栽培で2.5ヘクタールの面積の白ネギを育てています。
取材に訪れた1月は、ちょうど5月からの繁忙期が落ち着いた頃。2月〜4月は農閑期として、由布岳の雄大な自然を愛でながら、ゆっくり土づくりに励んでいるのだとか。
現在は「ネギの坂田」の代表を務める傍ら、白ネギ栽培のスペシャリストとして大分県中部地区の白ネギ栽培指導員、大分県由布市の白ネギ生産部会の特別指導員、大分県農業青年連絡協議会の事務局長なども務めています。
大分県は白ネギの生産量が全国でも有数の産地。しかし、坂田さんが選んだ由布市のある大分県中部エリアは白ネギの生産がそれほど盛んな地域ではありませんでした。
知識と経験が豊富な坂田さんが、それでも由布市で勝負に出た理由はなんだったのでしょうか。

「今後の気候条件を考えると葉物野菜のひとつである白ネギを栽培するには、平地より、高冷地の方が育てやすいだろうと思いました。また、高冷地なので他のエリアでは白ネギがつくれない時期にも出荷できる。そういう意味では前例はなくても、実績は作れそうだなと思いました。独立にあたって“、県の方にも大分県中部エリアにおける白ネギ栽培の礎になるつもりで頑張って”と声を掛けてもらい、たくさんのサポートもしていただきました」。
実際に由布市で2年間、白ネギを育ててみた手応えはどうでしょうか。
「この辺りの土壌は、阿蘇の火山灰と由布岳、鶴見岳の火山灰がブレンドされた良質な黒朴土。水捌けもよく、土壌の養分も豊富です。気候的にも虫がつきにくいため、農薬の量も少なくて済む。最初はわからなかったけど、この場所で2回の収穫を終えた今、改めて恵まれた土壌にあることを実感しています」
と話す坂田さんは、すでに周囲の畑を追加で5町ほど借りているという。害獣除けの柵の設置を待つ1年の間に土作りをしながら、今後はさらに栽培面積を広げていく予定だとか。
理想の白ネギ栽培のポイントを尋ねると
「量を平均より多く採れるかどうかも、もちろんひとつの指標にはなりますよね。でも量が取れたら正解というわけではないと考えています。固定のお客さんがつくとか、地域の気候を生かして周りが作れない時期に作るとかですね。そこで勝負するとすれば、年間通じて涼しい気候条件と、ゆたかな土壌を持つ由布市での白ネギ栽培の勝算は十分あります。露路栽培なので作業の手間がかかりますが、寒暖差のある方が白ネギは美味しく育ちますし、土地と人手さえあれば簡単に規模拡大できるというメリットもあります。何より田舎ならではの人間関係の中で、食べ物を作っているということ自体が誇らしいですね」との答え。

いつだって白ネギでいっぱい
2020年には佐賀県で開催された九州・沖縄地区青年農業者会議の「プロジェクト発表部門」で、坂田さんは仲間とともに最優秀賞を受賞します。内容は白ネギ栽培のネックになっていた育苗期間の長さと、定植にかかる手間を「固化培土」によって解決するというものでした。
青年同志会のメンバーと2016年から育苗の研究を開始。淡路島で玉ネギ用の培土を作っているメーカーに問い合わせ、白ネギ専用の固化培土『スミソイル』を開発します。2年間の効果検証の結果、平均90日から60日まで育苗期間短縮できたことにより、苗の生産性が向上し、規模拡大につながるなど、想像以上の効果が見られたと言います。
教科書には載っていない独自の方法論を編み出す姿勢は、これまで試行錯誤してきた努力の賜物です。
「白ネギは葉もの野菜の中でも難しい部類の作物。栽培期間も6ヶ月と長いので、夏場は、台風や高温・乾燥、冬場は積雪など、さまざまな気候条件に振り回されます。元々白ネギの原産国は中国北部で、乾燥していて寒さも厳しいモンゴルに近い場所。九州とはまったく違う気候を好む作物を育てようとしているので、難しいはずですよね。鳥取や鹿児島など各地に生産技術を学びに行きますが、なかなか思うようにはならないですが、そこが楽しい。もはや仕事も趣味は、白ネギ作りです(笑)」。
何事も究めていく過程が楽しむ坂田さんは、手間がかかるところも作物を育てる醍醐味だとか。白ネギの成長に応じて1作の間に6回ほど土を盛り足す、その手間こそ作物の味や見た目の美しさを生むといいます。
「以前、台風で白ネギが倒れてしまって2日ほど落ち込んだ後、白ネギが少しずつ立ち上がってきた時の感動はひとしおでした。僕もこうしてはいられない!と力をもらいましたね」。
県の方もそうした坂田さんの情熱に共感し、一緒に勉強する姿勢で寄り添ってくれるのだとか。機械を購入する際には補助金も活用しながら、由布市における白ネギ栽培を広める先駆者として、地域のため、消費者のため、周りの生産者のため“三方よし”の精神で日々仕事に取り組んでいます。
今では神奈川のご両親も現在は玖珠町に暮らし、白ネギの繁忙期には手伝いに通ってくれているとか。趣味を聞くと「ネギ」と答える坂田さん。休みを作って、ともに白ネギ栽培に励む奥さまと愛車で四国巡りをしたり、温泉地へ出かけたりすることも楽しみなのだとか。
今後の目標は、新規参入しやすい農業づくり。「農業を、子どもたちのなりたい職業にしたい」と話す坂田さん。
大事なことは、農業を好きになること。
そして自分なりの信念を持つこと。
「“社会貢献をしたい”と明確に口に出して言ったことはないけど、自分のアクションが周りといい形でつながっていけばいいなという思いは常にあります。結局は、熱意と周りと繋がる心意気さえあれば、技術を教えてくれる人もお金もなんとかできると思っています」。

周りの人を惹きつける力を持つ
地形も気候も、天候も。農業は、都市のように人間に都合の良い設計ではないけれど、それを技術と知恵とチャレンジ精神で乗り越えていくのもまた農業の魅力。
「白ねぎは食卓の主役にはならないけれど、どんな料理も引き立てる、なくてはならない存在です。僕も地域にとってそういう存在であり続けられたらいいのかなって。地域を盛り上げていくのは、結局のところ人間同士のつながりですからね」。
大分県は経営計画の策定から営農開始後のフォローアップまで充実した体制で就農や企業の農業参入を支援しています。農林水産業の会社に就職したい人も大歓迎です。
詳しくは
農林水産業・就業総合サイト「おおいたで働こう」
https://nourinsui-start.oita.jp/
のイベント情報をご覧ください。
サイト内のメールフォームからのお問い合わせも随時受付中です。
また、大分県では農業に興味関心のある方等を対象に東京、大阪、福岡、大分で相談会を開催しています。
この相談会の情報は以下をご覧ください。